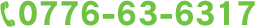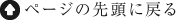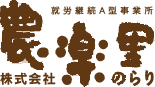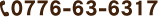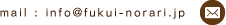かきもち編
かきもちの作り方の利用者用作業マニュアル
- 安全性・食品衛生を考えた服装
- 前日にもち米を研ぐ、浸漬
- 水切り、蒸す、餅つき、半乾燥、裁断、乾燥、揚げる、袋詰
服装
-

服装はマスク、白衣、帽子、ゴム手袋を着用
洗米、浸漬、水切り、蒸す
-

前日にもち米を洗う、研ぐ、浸漬
最初は多めの水を注いで、すぐに捨てる
もち米を研ぎ3回程度水を入れる
水が透明になるまですすぎ、10時間ぐらい浸漬 -

餅つきの日にもち米をざるにあげ、水気をきる
-

セイロに蒸し布を敷く
水を切ったもち米を広げる
蒸し布を引き上げ、空間をなくす
モチ米に蒸気の通り道を作る -

蒸し器の上にもち米を入れたセイロを置く
セイロを同じ向きに、5段までとする -

蒸し器の排水レバーを閉める
-

水の元栓を開き水を入れる
-
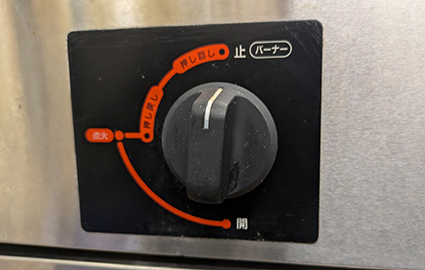
ガスの元栓を開き、つまみを押し込んで左に回し点火する
餅つき
-

1時間30分ぐらいで蒸し上がる(芯がないか確認)
一番下にラックを合わせてレバーを右に回す
6セイロからは蒸し時間は1時間 -

持ち上がったら一番下のセイロを引き出す
-

自動餅つき機を動かす
「羽根入」を押し羽根を運転させる -

蒸したもち米を自動餅つき機に入れる
蒸し布が厚いので火傷に注意 -

蒸し布を取り除く
-

塩を入れる
豆以外のゴマや昆布等の食材一品を入れる -

「杵入」を押してもちをつく
-
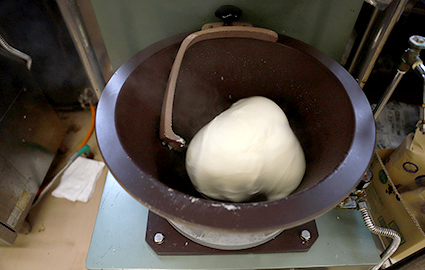
約5~6分つく、米粒が残る場合は餅つきを延長
-

包丁にもちが付かないように食用油脂を吹きかける
両面に吹きかける -

もち切りシートに片栗粉を敷く
-

餅を取り上げ、「停止」を押し羽根を止める
もちの形成
-

つき終わったもちをもち切り台に移す
-

もち箱に入る大きさに切る(4等分)
-

もちをもち箱の長さに伸ばし、もち箱に入れる
-

もちを隅まで手で伸ばす
-

凹凸がないように広げる
-

冷蔵する(切りやすくするため)
※ ガスの元栓を閉める
※ 水の元栓を閉め、蒸し器の中にある水を排水する
もちの裁断
-

もち箱からを外す
-

電源を入れる
-
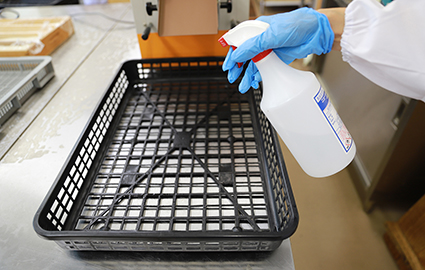
トレーを消毒
-

もち切り機にもちをセットする
-

もちを裁断し、ほぐす
-

トレーを消毒
乾燥
-

カットしたもちを重ならないように広げる
-

乾燥機に入れて乾燥させる(除湿乾燥)
季節により乾燥期間を調整
かきもちの作り方
-

モチが重ならないように並べる
-

レンジにかける
-
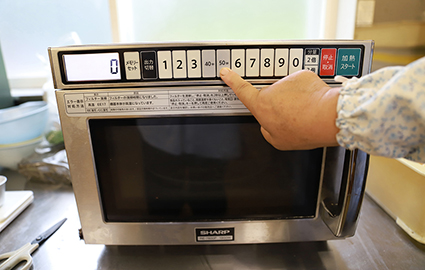
レンジかけ(50秒設定)
-

受け皿が熱いので軍手を着用
-

フライヤーのパネルをONにして一定の温度に上げる
-

耐熱用ゴム手袋を着用
火傷に注意しながら揚げる
一定量の5種類を揚げ、その後、再度種類別にあげる -

油をきる
-

袋詰め
-

袋にシールを張る(冷やしている時)
-

冷やす(30分~1時間程度)
手で触れて確認 -

袋詰めは縦に「ごま」「昆布」「あおさ」の2種類を2枚、
その上に重ねて「豆」「白」を2枚、
「黒糖」1枚を入れる -
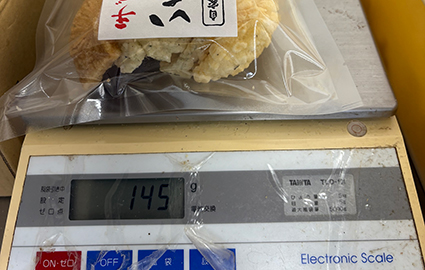
シリカゲルを入れて全体の重量を145g
-

封をする(約5秒)
-

完成
※ 一箱15袋づつ入れる