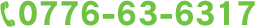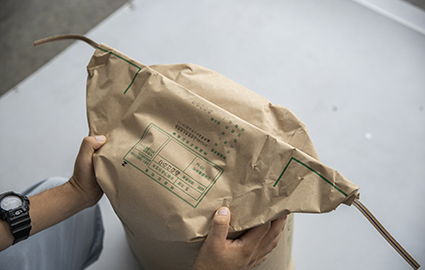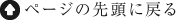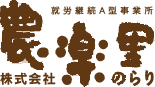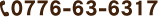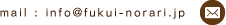精米編 Cms 05C
㈱サタケの小口精米ユニットCMS 05Cを使用した利用者用の精米工程マニュアル
- 当日に精米する玄米を倉庫から精米室に搬入、品種別・等級別に積む
- コンプレッサー、主電源等をON
- 玄米を荷受けホッパー投入⇒精米の白度、色彩選別機を通過した精米の確認
⇒計量器の容量セット⇒包装資材(紙袋)に入れ、紙袋を閉じる - コンプレッサー、主電源等をON
- 包装資材(紙袋)は、事前に必要枚数を確認、産年・品種・精米時期を押印
コンプレッサー、主電源、昇降機、精米ユニット、計量器の電源を入れる
-

コンプレッサーのスイッチを「運転」にする
-

ドライヤーのスイッチを「運転」にする
-

主電源のスイッチを「ON」にする
-

昇降機、精米ユニットのスイッチを「ON」にする
-

計量器の電源を入れる
精米ユニット、色彩選別機を動かす
-

精米ユニットの「確認」を押す
-

自動運転の場合は「自動運転」を押す
-

「運転」を押す
-

色彩選別機の「運転」を長押しする(1~2秒)
玄米の搬入・サンプル確認
-

昇降機の「運転」ボタンを押す
玄米の投入が終わったら「停止」を押す -

玄米投入口に玄米を投入
運転管理者等と玄米の品質等を投入前に確認する
周りに玄米が飛び散らないように投入
少しでも飛び散った場合は玄米を投入したら清掃 -

混米タンクのシャッタを手前に引いて(開けて)石抜機へ
混米タンクが空になり、全て玄米が石抜機に入ったら混米タンクのシャッタを戻す(閉める) -

精米機残留米排出の精米窓を開ける
-

サンプル採取トレイでサンプルを採取
-

精米の白度を標準精米と比較・確認
比較・確認後にサンプルを戻す白度が標準品より低い⇒設定電流値▲を押す
白度が標準品より高い⇒設定電流値▼を押す【例】低い⇒設定電流値「23A」を「24A」にする
高い⇒設定電流値「23A」を「22A」にする再度、白度を確認 運転管理者に連絡
-

色彩選別機の試料採取窓からサンプルスコップを投入
-

サンプルを丸カルトンに入れる
カルトンで確認⇒「白」又は「黒」カルトン -

「カメムシ」「ヤケ米」「異物」等がないか確認
「しらた(乳白粒)」は運転管理者が調整
運転管理者等に連絡運転管理者等は利用者と一緒に調整
- 選別対象物のアイコンをタッチ「ON/OFF」の設定
- 「感度の数値」をタッチ、感度バーをスライドし
調整 - 「運転」ボタンを長押し(3秒)すると運転が開始される
-
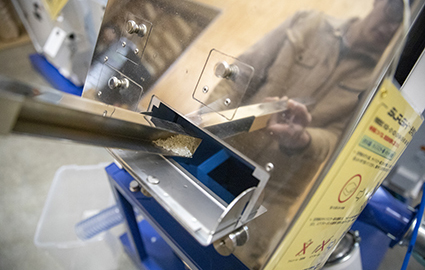
サンプルは試料採取窓から戻す
軽量・包装作業
-

運転前の点検⇒操作部電源スイッチを「入」にする
電源を「入」にして15~20分間おく(電流の安定)計量重量を設定
計量設定ボタンを2秒以上押す⇒数値入力ボタンで設定⇒「設定・登録ボタン」を押す -

袋受台を袋の高さに調整⇒袋を払出シュートにセット
-

「払出フットスイッチ」を踏み、精米を袋に入れる
-

定量の精米が入れば紙袋を閉じる
定量の範囲外となった場合は「払出OK表示」が点灯
「残量ボタン」を押し、払出フットスイッチを踏み排出
精米をする順番
- 特別栽培米コシヒカリ⇒コシヒカリ⇒ハナエチゼン
- 品種が変わった場合は、昇降機等は掃除機で吸引する。精米室を清掃し、コンタミを防止する
- いつもと音・臭い・振動等が異なる場合は、運転管理者等に直ちに連絡する
- 分からないこと、不安なことなどがあれば何でも運転管理者等に連絡する
製品精米の印字
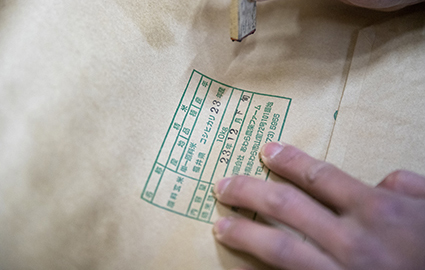
袋の印字「品種名」「内容量」を確認
・産年の下に収穫年をゴム印で押印
・精米時期をゴム印で押印
【例】2023年産米を2024年4月1日に精米した場合
産年の下に「23年」、精米時期に24年4月上旬
「上旬」1日~10日、「中旬」11日~20日、
「下旬」21日~月末
特別栽培米の場合のシール対応
-

特別栽培米は新ガイドラインの表示シールを貼る
-

特別栽培米はさらに認証シールを貼る
作業が終わる場合
- 1の⑤⇒④⇒③⇒②⇒①の順にスイッチを切る
- 定量の範囲外となった精米は「はかり」で重さを図り、袋にその重さを書く
- 整理・整頓・清掃を行う、昇降機の下は必ず掃除機で吸引する
- 製品精米は、販売先別に置く、指示書とあっているかを確認する
- 製品精米は、品種別、内容量別に置く
- 製品精米の数量と指示書の数量が品種別、内容量別にあっているかを確認する
- 精米施設を離れる場合は運転管理者等に連絡し、施錠する
袋詰め編
紙袋を折る(10㎏以下)
-

精米を紙袋に入れ紙袋の表を手前にする
-

紙袋の両サイドを折る
-

紙袋を向こうに3回折る
-

紙袋の右側を折る
-

紙袋の左側を折る